社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~㊽
2025/05/14
(1)債務超過部分を債務控除の対象とするための要件
債務超過分部分は無限責任社員の連帯債務であり、債務控除の対象となるのは被相続人が負担することとなることが確実と認められる債務相当額であるということ、つまり、
・①相続開始時に評価会社の経営が行き詰まり、
・②債務超過が著しい場合で、
・③当該債務について死亡した無限責任社員が責任を負うことは確実で、
・④かつ相続において負担すべき金額が確定している場合に、債務超過部分を債務控除に使えるということになります。
(2)事実認定の問題
「なぜ」1人株式会社を1人合名会社に組織変更したかということについて経済的合理性が問われます。そしてその疎明は納税者がすべきものです。納税者側の理論武装として何かしらの根拠を考えなければならないことになりますが、会社法上認められた組織変更というシステムということはあるものの、1人の株式会社を1人の合名会社にするということに関して経済的合理性がある理由は思いつきません。
当該プランニングについては実務上の事例集積段階にあるので、実行する場合は慎重に行う必要があります。事実認定の問題について、下記のような見解もあります。当該プランニングは、所得税基本通達64-3や相続税法基本通達14-3とのバランスの問題がとれているか、という観点からのチェックも入る余地があり得ます。
【所得税基本通達64-3】
(回収不能額等が生じた時の直前において確定している「総所得金額」)
64-3 令第180条第2項第1号《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》に規定する「総所得金額」とは、当該総所得金額の計算の基礎となった利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額(損益通算の規定の適用がある場合には、その適用後のこれらの所得の金額とし、赤字の所得はないものとする。)の合計額(純損失の繰越控除又は雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、当該合計額から総所得金額の計算上控除すべき純損失の金額又は雑損失の金額を控除した金額とする。)をいうものとする。
(注)上記の譲渡所得の金額とは、長期保有資産(法第33条第3項第2号《譲渡所得》に掲げる所得の基因となる資産をいう。)に係る譲渡所得であっても、2分の1する前の金額をいうことに留意する。また、一時所得の金額についても同様である。
【相続税法基本通達14-3】(保証債務及び連帯債務)
14-3 保証債務及び連帯債務については、次に掲げるところにより取り扱うものとする。
⑴ 保証債務については、控除しないこと。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除すること。
⑵ 連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除し、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者(以下14-3において「弁済不能者」という。)があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も当該債務控除を受けようとする者の負担部分として控除すること。
合名会社等の無限責任社員も、会社が返済できない状況にあり、かつ主たる債務者に求償しても返還を受けることができない場合に債務控除の対象となるものであって、
・会社が債務を返済することができないかどうかは事実認定の問題であり、単に債務超過であれば債務控除ができるというものではないという見解です。
相続直前に同族法人経由で意図的に債務控除を作出して、相続税法64条で否認された事例があります。同族法人で不動産を時価よりはるかに高額で借入金により購入し、その借入金の連帯保証人に当該同族法人の代表者がなります。当該代表者がなくなった場合、その連帯保証分は債務控除の対象とできます。
これについて裁判例では、法人を経由した相続税の圧縮行為とみなして相続税法64条を発動しています。
※伊藤俊一先生の講義は『日税ライブラリー研修』でご受講が可能です。
『日税ライブラリー研修』の詳細・申込はこちら。最新の伊藤先生の研修はこちら。





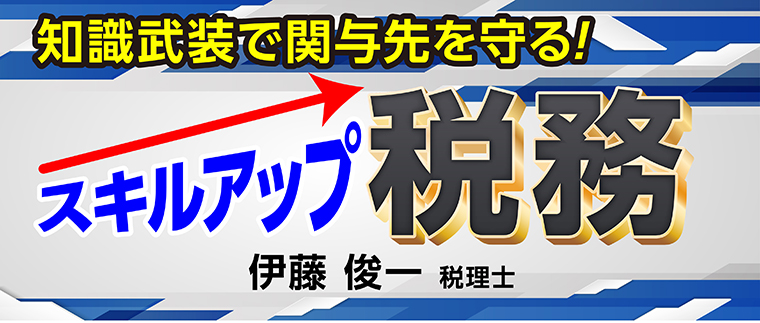




 無料登録はこちら
無料登録はこちら